生成AI(ChatoGpt等)を使うときの6つの注意点を解説します。
〜AIは万能じゃない。限界と正しい使い方を理解しよう〜
ChatGPTをはじめとする生成AIは、まるで何でも知っているかのように振る舞い、
まさに「話せる検索エンジン」として私たちの日常に入り込んできました。
僕も使っていて驚きでした~
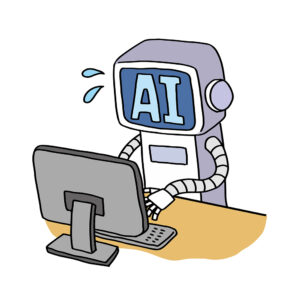
質問すれば即座に答えが返ってきて、ちょっとした相談にも乗ってくれる──
まさに未来のパートナーのような存在です。
僕も驚きながら使いましたよ~
でも使いながら欠点もあることに気が付きました~
平気で間違います、平気でボケます。
もちろんしょっちゅうではないですよ。
なので、それなりのその分野での見識が必要です。
あと検証する癖を常に持っておくことです。
また、ここで注意すべきは「万能な存在ではない」ということ。
特に以下のような分野では、ChatGPTを過信すると大きなリスクを伴う場合があります。
本記事では、ChatGPTを安全かつ賢く使うための6つの注意点を、
実例を交えてわかりやすく解説します。
目次
1。コーディング:「書ける」 でも 「信じるな」
ChatGPTはプログラミングのコードも書けます。
特にHTMLやPythonなど、簡単な構文を使ったスクリプトであれば非常に優秀です。
実際、多くの開発者が初稿のコード生成に利用しています。
ただし、AIが書いたコードは必ず人間が確認する必要があります。
エラーを含むコードや、セキュリティ上問題のある記述が混ざっていることも少なくありません。

特に初心者の方が「これでOKだろう」と鵜呑みにしてしまうのは非常に危険です。
最近では「Codex」などのAIコーディングツールも登場していますが、
現段階ではまだ完璧とは言えず、専門家によるチェックが必須です。
まだまだチェックが必要なんです。
2.心理セラピー:感情の複雑さは理解できない
悩みや不安を誰かに聞いてもらいたいとき、ChatGPTに話しかける人も増えています。
たしかに、日々のちょっとした悩み──
たとえば「やる気が出ない」といった話題には有益なヒントをくれるかもしれません。

しかし、深刻な悩みや精神的な不調については、絶対に人間の専門家に相談してください。
AIは人の心を完全に理解するようには設計されていません。
あなたの背景や感情のニュアンスを正しく読み取ることはできず、
結果としてアドバイスが逆効果になることさえあります。
3.医療アドバイス:診察はできない
「ちょっと頭が痛いけど、病院に行くほどじゃない…」
そんなときにChatGPTを使って症状を調べたくなる気持ち、よくわかります。
しかし、AIは医師ではありません。診察も検査もできません。
よくあるのが、AIがネット上の情報を集めて
「可能性のある病名」をリストアップしてくれるケース。
でもそれは診断ではなく、単なる情報の引用にすぎません。
ChatGPTは「私は医師ではありません」と注意喚起しますが、
それでも答えを求めたくなってしまうのが人間心理です。
☆健康に関する判断は、必ず医療機関で受けましょう。
☆AIはあくまで参考程度にとどめてください。
ただし、参考程度なら全くかまいません。
4.法律アドバイス:自己判断はトラブルのもと
法律もまた、AIが扱うにはハードルが高い分野です。
たとえば契約書のチェックや、トラブル時の対応策などをChatGPTに聞くと、
それらしく答えてくれるかもしれません。
でも、法制度は国や状況によって異なり、ケースバイケースの判断が必要です。
もし間違った情報に基づいて行動してしまった場合、
取り返しのつかない結果になる可能性もあります。
弁護士の代わりになることは法律で禁止されています。

AIが提供する法律情報はあくまで「参考知識」。実際の判断や対応は、
必ず弁護士などの専門家に相談しましょう。
5.詳細なリサーチ:ハルシネーションに注意
ChatGPTは、あたかも「すべてを知っている」かのように情報を提示してくれます。
しかしその中には、もっともらしいけど間違っている情報
──いわゆるハルシネーションが含まれていることがあります。
たとえば、出典が存在しない本や論文を挙げてくることも珍しくありません。
引用が必要な場面では、必ず一次情報を確認し、裏付けを取るようにしましょう。
2025年からは「Deep Research」という精度の高い調査ツールもChatGPTに搭載されましたが、
それでも誤情報がゼロになるわけではありません。
最終的な検証は、やはり人間の役目です。
6.金融予測:その情報、本当に信用できますか?
「この株は上がる?」「仮想通貨はいつ暴落する?」
こういった質問にChatGPTを使いたくなる人も多いでしょう。
でも、ChatGPTは未来を予測できません。
AIが提供する情報は、過去や現在の公開データに基づいたものであり、
独自に市場分析をしているわけではありません。
中には、出典の怪しい予測記事やブログからの引用もあるため、
投資判断に使うのは非常にリスキーです。
金融の判断は、信頼できる専門家や複数の情報源に基づくべきです。
ChatGPTはあくまで「補助ツール」。判断はあなた次第(自己責任)
ChatGPTは、調査やアイデア出し、文章作成など、多くの場面で非常に役立ちます。
しかし、万能な存在ではありません。
「使い方を間違えると、逆にリスクが高まる分野」があることを忘れてはいけません。
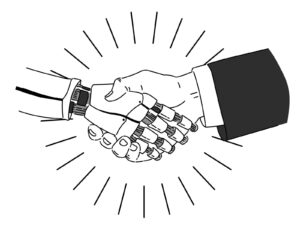
以下の6つは、ChatGPTの使用に特に注意が必要な領域です。
- コーディング(自己チェック必須)
- 心理相談(深刻な悩みは専門家へ)
- 医療(診断や処方は不可)
- 法律(判断をAIに任せない)
- 詳細なリサーチ(情報は裏取り必須)
- 金融予測(未来を当てる力はない)
これらを理解したうえで活用すれば、ChatGPTはあなたの大きな助けになるはずです。
AIと上手に付き合いながら、情報を正しく判断できる目を育てていきましょう。
あくまでも「自己責任」です。

